「電動バイクに乗ってみたいけど、免許が必要?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、一部の例外を除き、電動バイクに乗るためには免許が必要です。また、電動バイクの定格出力によって必要な免許も異なります。
この記事では、電動バイクに必要な免許の区分について解説します。電動バイクの選び方や維持費、新設された区分である特定小型原動機付自転車についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
はじめに:電動バイクは原付免許で乗れる?
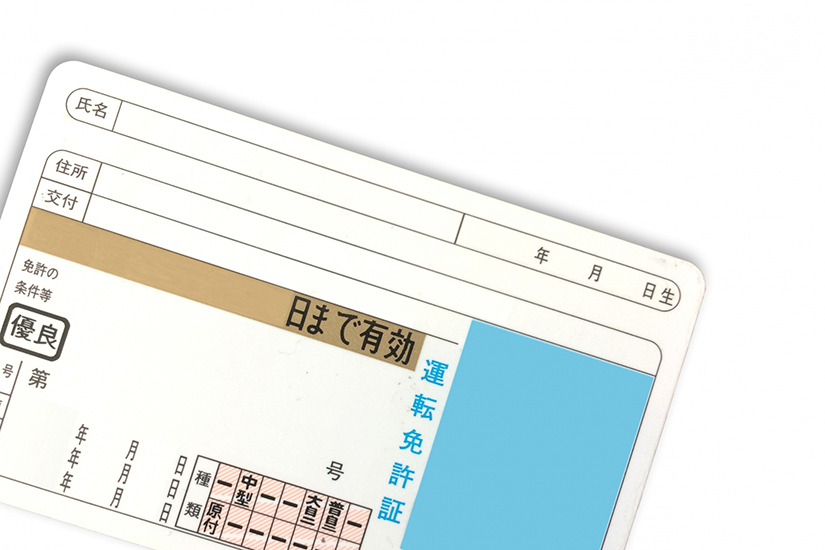
電動バイクは、定格出力に応じて必要な免許が異なります。
定格出力が0.6kW以下の場合は、原付一種を運転するための免許が必要です。原付免許や、普通自動車免許で運転できます。
定格出力が0.6kWを超える電動バイク(原付二種)の運転には、小型限定普通二輪免許以上が必要です。一般的な原付免許では運転できないため、ご注意ください。
電動バイクの免許区分は「定格出力」で決まる
電動バイクの免許区分は、定格出力で決まります。電動バイクに必要な免許やナンバープレートを、定格出力ごとにまとめて解説します。
定格出力ごとの免許・ナンバープレート対応表
電動バイクの定格出力ごとに必要な免許と、ナンバープレートの色を対応表にしました。ぜひ参考にしてみてください。
| 定格出力 | 必要な免許 | ナンバープレートの色 |
| 〜0.6kW | 原付免許、普通自動車免許 |
|
| 0.6kW〜1.0kW | 小型限定普通二輪免許 |
|
| 1.0kW〜20kW | 普通二輪免許 |
|
| 20kW〜 | 大型二輪免許 |
|
【2023年7月〜】新設された「特定小型原動機付自転車」とは?
2023年7月1日の道路交通法改正で、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」という車両区分が新たに新設されました。
特定小型原付の例として電動キックボードなどがありますが、実際は以下の基準を全て満たす車両が該当します。
- 車体の大きさは、長さ190㎝以下、幅600㎝以下であること
- 原動機として、定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること
- 時速20㎞を超える速度を出すことができないこと
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯が備えられていること
これらに加え、
- 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
- 標識(ナンバープレート)を取り付けていること
引用:警察庁|特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
特定小型原付に該当する車両であれば免許不要で運転可能ですが、16歳未満が運転することは禁止されています。また、最高速度は20km/h以下です。
電動バイクや原付と同様にナンバープレートの取得が必要です。電動バイクはヘルメットの着用義務がありますが、特定小型原付では努力義務とされています。
また、特定小型原付では、標識に「自転車を除く」「軽車両を除く」とある場合は、一方通行を逆走することも可能です。
原付免許で乗れる電動バイクの選び方と価格相場

原付免許で乗れる、定格出力0.6kW以下の電動バイクについて、選び方と価格相場を解説します。
選ぶ際の3つのポイント
電動バイクを選ぶ際のポイントは
- 用途に合った航続距離で選ぶ
- 充電方法を確認する
- デザインや機能性で選ぶ
です。
通勤・通学で毎日使うのか、近所の買い物でたまに使うのか、用途を明確にしたうえで、必要な航続距離を満たすモデルを選ぶことが重要です。
また、充電方法で選ぶのも重要なポイントです。自宅のコンセントで充電できるか、バッテリーを取り外して室内で充電できるタイプかなど、ライフスタイルに合った充電方法のモデルを選ぶことをおすすめします。
愛着が持てるよう、デザインの好みや機能性の使い勝手も重要なポイントです。デザインの好みはもちろん、収納スペースの有無やスマホ連携機能など、付加価値にも注目してみましょう。
価格帯の目安
原付一種クラスの電動バイクであれば、15万円〜30万円程度が相場です。
また、ガソリンバイクと電動バイクを比較した場合、燃料代は電動バイクの方が安い傾向にあります。1km走行に必要なガソリン代と電気代を比較した際、電気代の方が基本的に安くなります。また、電動バイクはエンジンオイルの交換も不要なため、メンテナンス費用もガソリンバイクに比べて安く抑えることが可能です。
免許以外にも必要!電動バイクの税金・保険・車検
電動バイクには免許のほか、税金や保険、車検などの手続きや費用も必要です。電動バイクの維持のために必要な費用や手続きについて解説します。
税金(軽自動車税)
電動バイクの場合、原付と同様に軽自動車税がかかります。定格出力に応じた年間の軽自動車税額は、以下の通りです。
- 原付一種(定格出力0.6kW以下):2,000円
- 原付二種:定格出力に応じて税額が異なります。
- 0.6kW超〜0.8kW以下の場合:2,000円
- 0.8kW超〜1.0kW以下の場合:2,400円
自賠責保険
電動バイクの場合、原付と同様に自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。加入の手続きはコンビニなどでも手軽に行えるので、必ず加入しておきましょう。
また、任意保険への加入も強くおすすめします。自賠責保険の補償内容は、事故を起こした場合の被害者のケガや死亡に対する補償のみです。被害者の車体に対する補償や、自分が加害者となった場合のケガの補償や車体への補償は任意保険でないとカバーできません。自賠責保険に含まれていない補償をカバーするためにも、任意保険にも加入しておきましょう。
車検
定格出力1.0kW以下の原付一種・二種の電動バイクには車検がありません。
また、定格出力が1.0kWを超える電動バイクのうち、『軽二輪(125cc超250cc以下相当)』に分類されるものも車検は不要です。
ただし、同じ1.0kWを超える電動バイクでも、『小型二輪(250cc超相当)』に分類される場合は車検が必要ですのでご注意ください。
安全に乗るためには定期的なメンテナンスが重要です。自分で日頃から車体をチェックしたり、購入した店舗や修理店などで定期的にメンテナンスしたりするようにしましょう。
まとめ:購入前にレンタルで試すのも賢い選択
電動バイクに乗る際は、定格出力に応じて必要な免許が異なります。乗りたいと思っている電動バイクと、運転に必要な免許、維持費などをあらかじめ把握しておくことが重要です。
どの電動バイクにしようか迷っている場合や、電動バイクかガソリンバイクで迷っている場合などは、レンタルで試すのもおすすめです。
マンスリーバイクでは、さまざまな車種のバイクを月額でレンタルすることができます。千葉県近郊でレンタルバイクをお探しの場合は、ぜひお近くの店舗をご利用ください。





